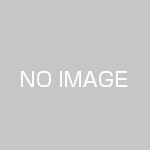パレート効率的な状態の事例|ミクロ経済学(21)

Contents
パレート効率の定義
ミクロ経済学において、重要なキーワードの一つに、パレート効率という言葉がある。
前節の余剰は、一つの財に焦点を絞って考えた論点だが、パレート効率性では、複数の財を考慮にいれて考える。
パレート効率の定義は以下の通り。
「だれかの効用をさげない限り、誰の効用も上げられない状態」
つまり、余剰で言うところの社会的総余剰が最大の状態(=完全競争市場)となる。
パレート効率性の事例
パレート効率的な事例を考えてみる。
私はサッカーが大好きだが、友人は野球が大好きだ。
また、私は野球がわからず、彼はサッカーのたのしさを知らない。
ここに、ワールドカップのチケットと、WBCのチケットがある。
私がワールドカップのチケットもらう。彼にはWBCのチケット上げる。
これはパレート効率的な状態だ。
それでは、ワールドカップのチケットのみ二枚あった場合はどうだろうか。
私がワールドカップのチケットもらう。彼にも申し訳ないからもう一枚のワールドカップのチケットをあげる。そうすれば彼も少しは喜ぶだろう。
しかし、これはパレート効率的でない。
何故なら二つとも私がもらった方が、ワールドカップチケットをもらった彼の満足度より、満足度がたかいからだ。
全体としては、その方が効用は高くなる。
つまり、全体として最大限の効用を生み出している状態がパレート効率的ということだ。
この例からもわかるように、パレート効率とは公平性とはまったく関係がない。
なお、余剰分析での、死荷重が発生している状態はパレート効率的でない。
何故なら、政府が介入を止めることによって社会全体の余剰は増えるためである。
photo credit: hans s via photopin cc
編集後記
重要なキーワードです。しっかり理解しましょう。
それにしても、図がないというのは、とても楽です(((^_^;)
▼▼▼続きを読みたい人は▼▼▼